こんにちは
れいほくTVです。
[inaka]お主は真顔というのかぁ。土佐の国から出たいのか?
だったら通行手形を見せェ[/inaka] [magao2]ディべお殿様、ここを通らせてください。[/magao2] [inaka]よろしい!ここを通るがよい[/inaka] [magao4]江戸時代、参勤交代などで高知県(土佐藩)から出るためにはこのようにしていました。
今回は大豊町の立川にある土佐最後の番所。
旧立川番所書院(以下、立川番所と記載)をご紹介します![/magao4]
立川番所について

引用:大豊ナビ
立川番所は愛媛・徳島県との県境に位置し参勤交代での番所として国境を警備していました。
海路で江戸へ行っていた時期もありましたが、風波の影響が大きいため陸路の移動へ変わった経緯があります。
現在の立川番所は住民や保存会により維持管理され、日曜日または祝日に一般へ内部を開放しています。
立川番所の建物をご紹介
立川番所の建物は川井惣左衛門勝忠(かわいそうざえもんかつただ)が寛政年間に建築したものとされています。
その後、明治時代で個人の所有物となり一部改築し旅人宿として営業していました。
現在の建物内は部屋と次の間などを含めて全部で9室。
各部屋には、貴重な物も展示しています。
[inaka]今回はその中でも行った時にぜひ見て欲しいお部屋と展示物をピックアップしますよ。[/inaka]上段の間

立川番所の一番奥にあるのが上段の間。
ここには一段上がっており、そこにはお殿様が座っていたと言われています。
上段の間の横にはお殿様専用の門があり、お殿様が外出の際はその門を使っていました。
大広間

大広間は全部で21帖。
立川番所で一番の大きさの部屋となっています。
こちらでは多くの旅人が休んでいたことでしょう。
この大広間にも展示物があります。
立川番所の展示物

立川番所には数多くの展示物があります。
昔の古い書物からお札まで立川番所には歴史があることを感じられるでしょう。
見学へ行ったら展示物にも注目です!
現在、これらの展示物も地元の方が守っています。
[magao4]地域の人の協力があるから守れているんだね♫
みんなさんも、足を運んで一緒に残して行くお手伝いを〜[/magao4]
国の重要文化財にも指定
立川番所は昭和49年(1974)、国の重要文化財にも指定され、大豊町の所有物となりました。
その後、昭和55年には総工費1億円をかけて解体し修復工事を実施。
現在は大豊町教育委員会と地域の住民によって維持されています。
毎月第三日曜日は立川御殿茶屋も営業

立川番所横には毎月第三日曜日には立川御殿茶屋が営業。
ここでは立川名物の立川そばや地元の山菜を使った料理が食べられます。
立川番所へ行かれる際は毎月第三日曜日に行くのもいいでしょう。
[magao2]月にたった1度!!!これは行かなきゃだ![/magao2]立川番所へのアクセス

立川番所には国道439号線から県道5号線(末広大豊店横交差点)で川之江方面へ行くことで立川に着きます。
車の場合、大杉駅から約20分。
立川番所入り口には上の写真の看板があります。
町営バス立川線の場合、大杉駅からは約40分です。
(注)現在は大雨の修復工事のため川之江方面からの道は通行止め(高知側のみ通行可)となっています。
まとめ

今回は立川番所を取り上げました。
建物内を見学する際は地域の方の解説もあり、とても楽しいひと時が過ごせます。
立川番所は毎週日曜日・祝日に地域の人の手により一般向けに開放。
みなさんも高知の歴史に触れてみませんか。

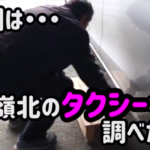
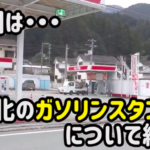

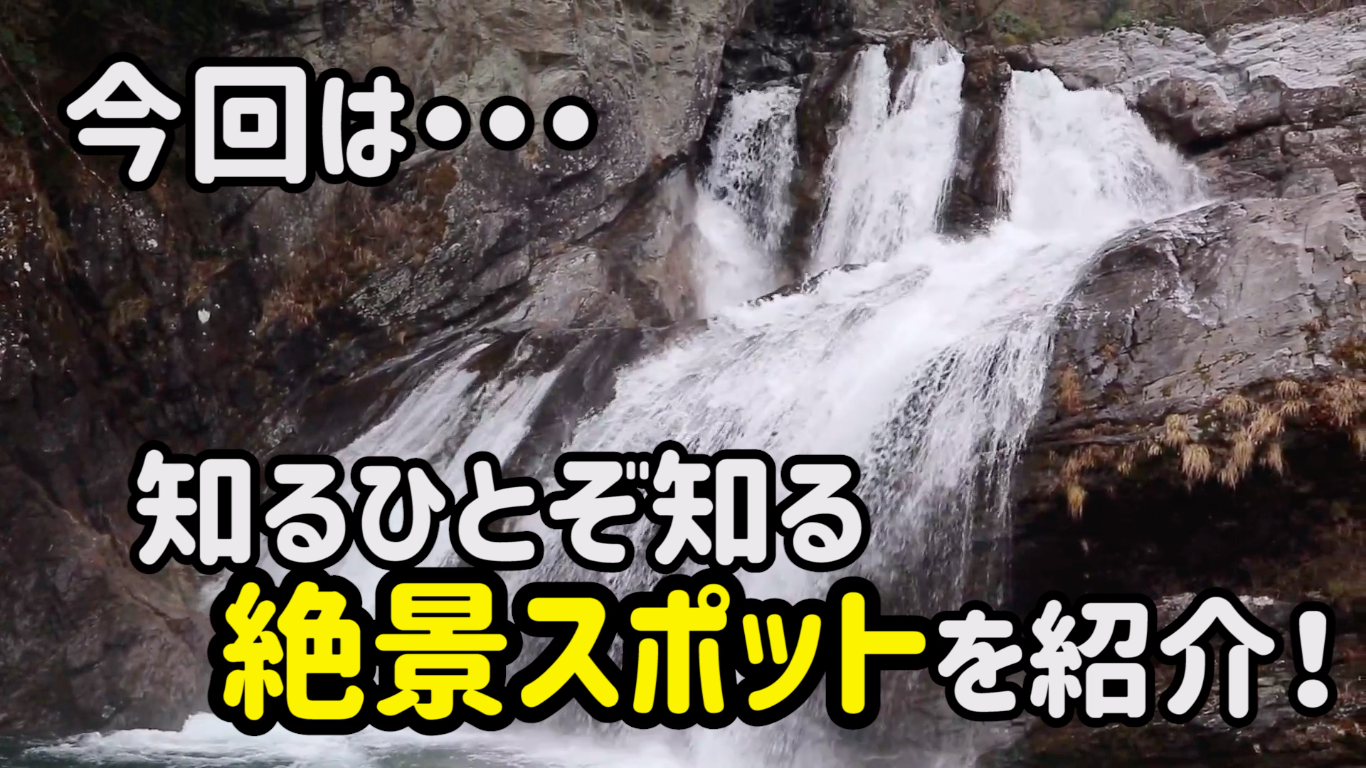
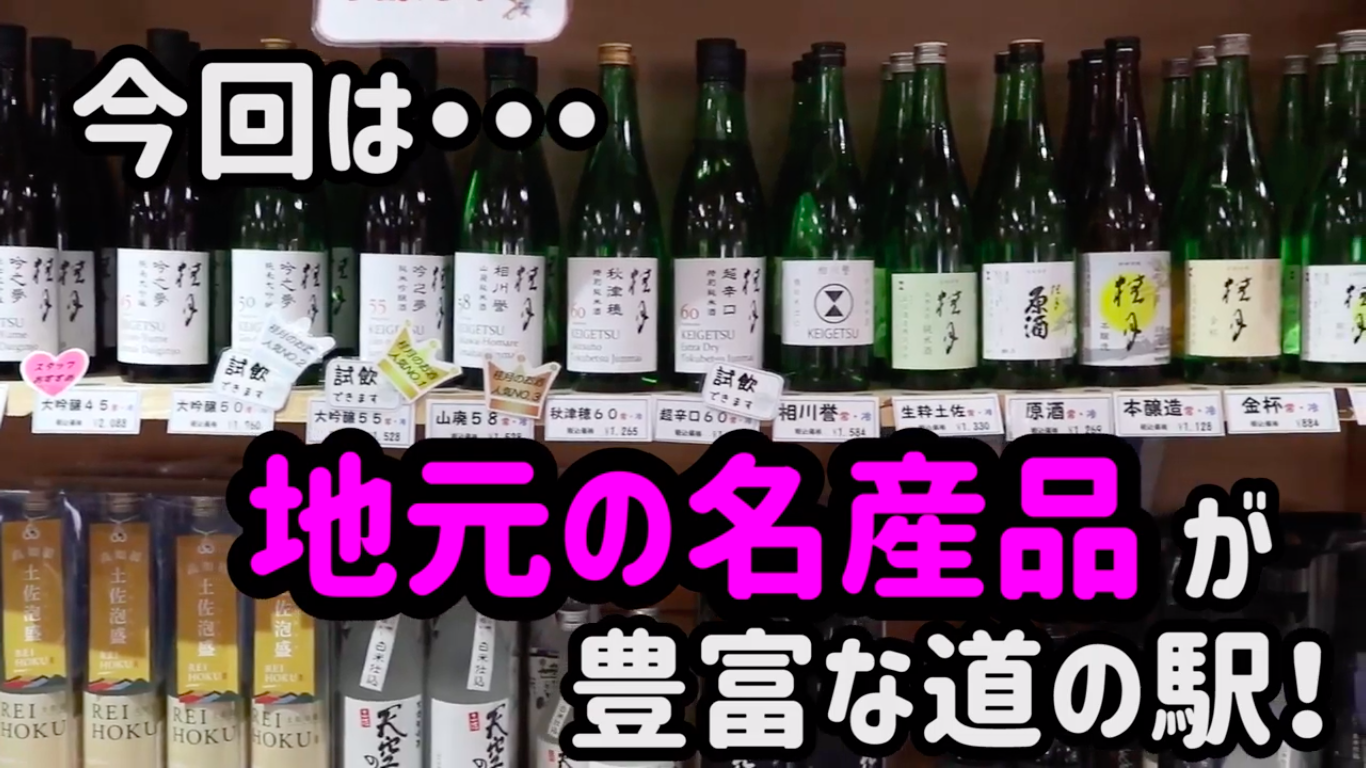
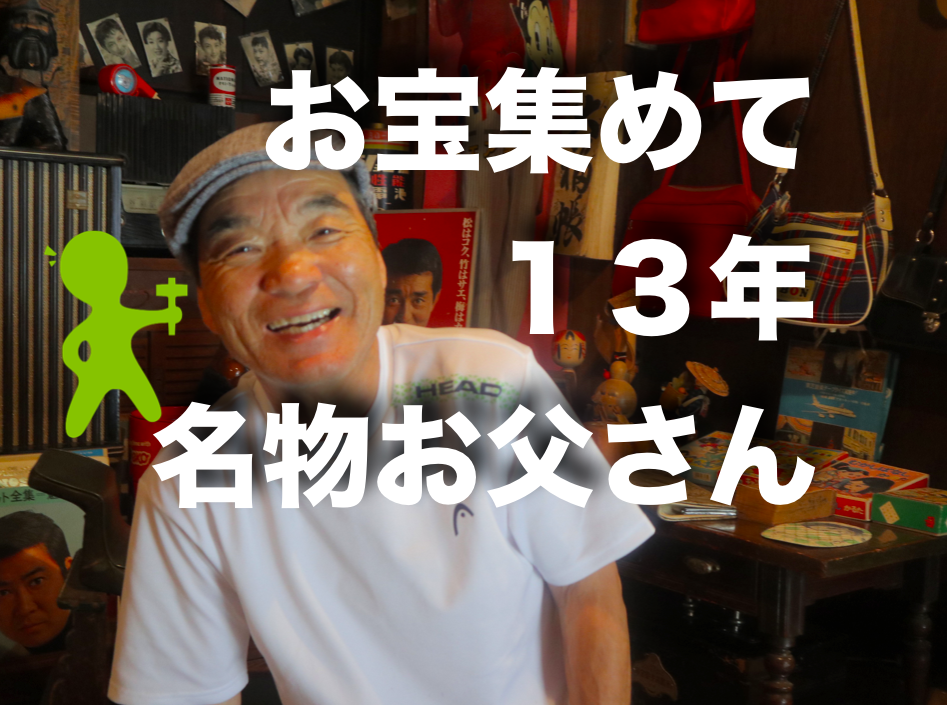
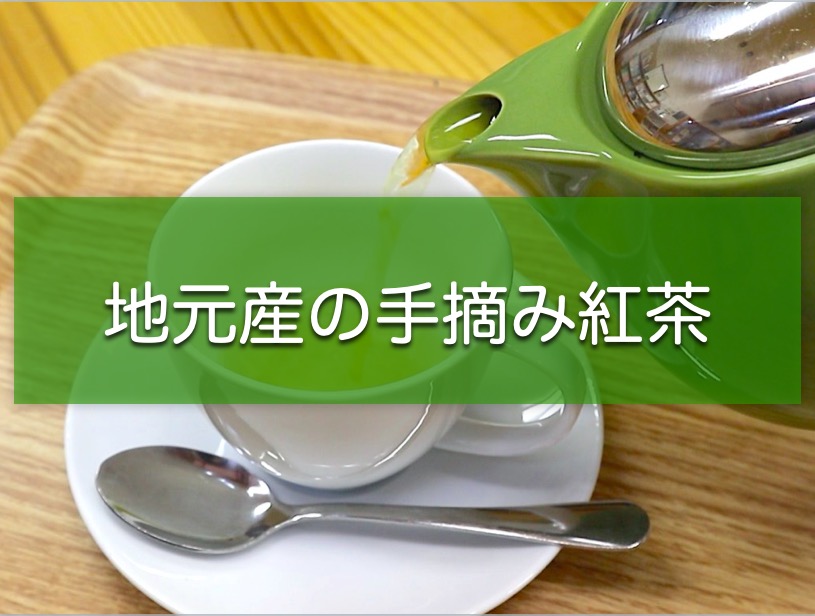
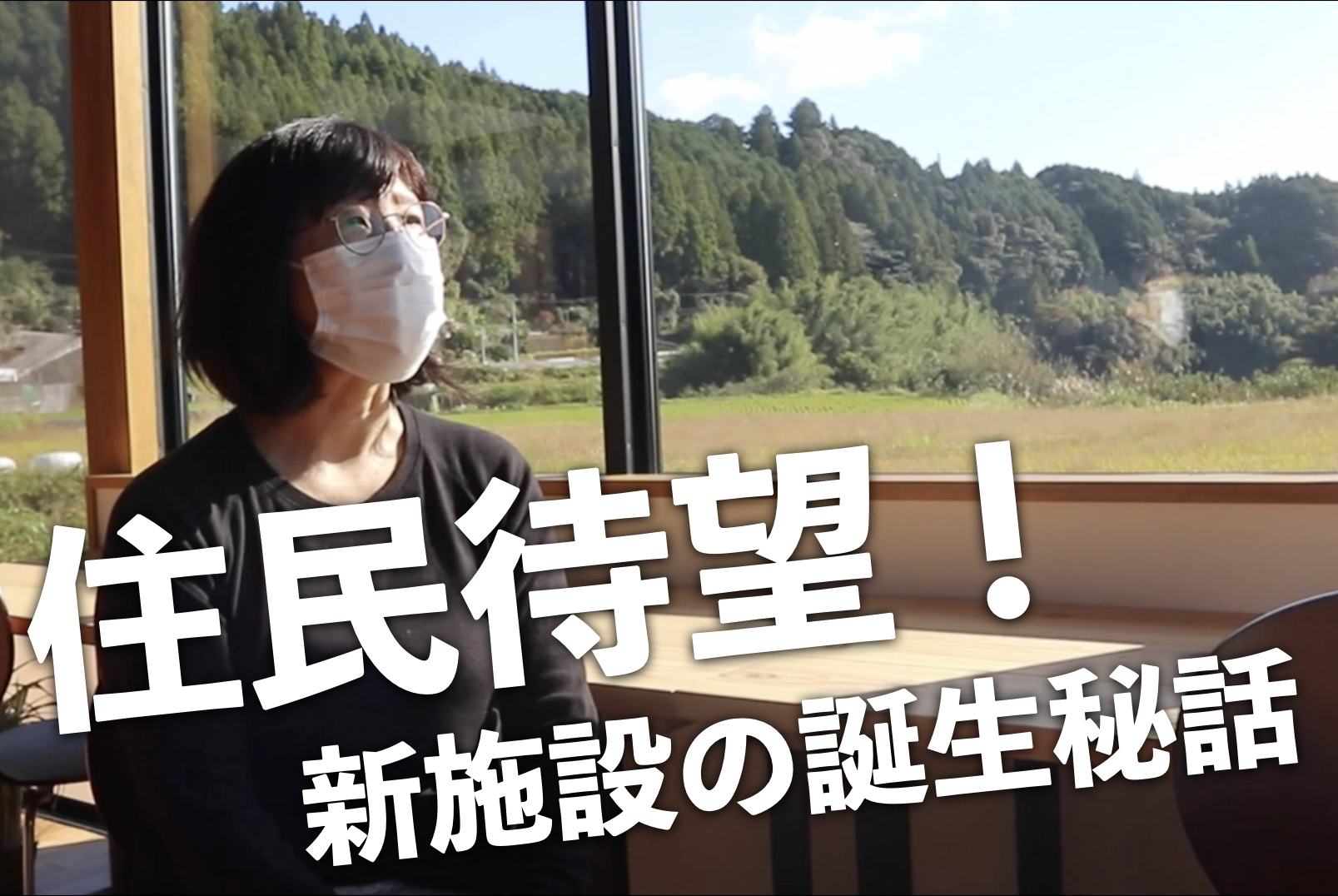

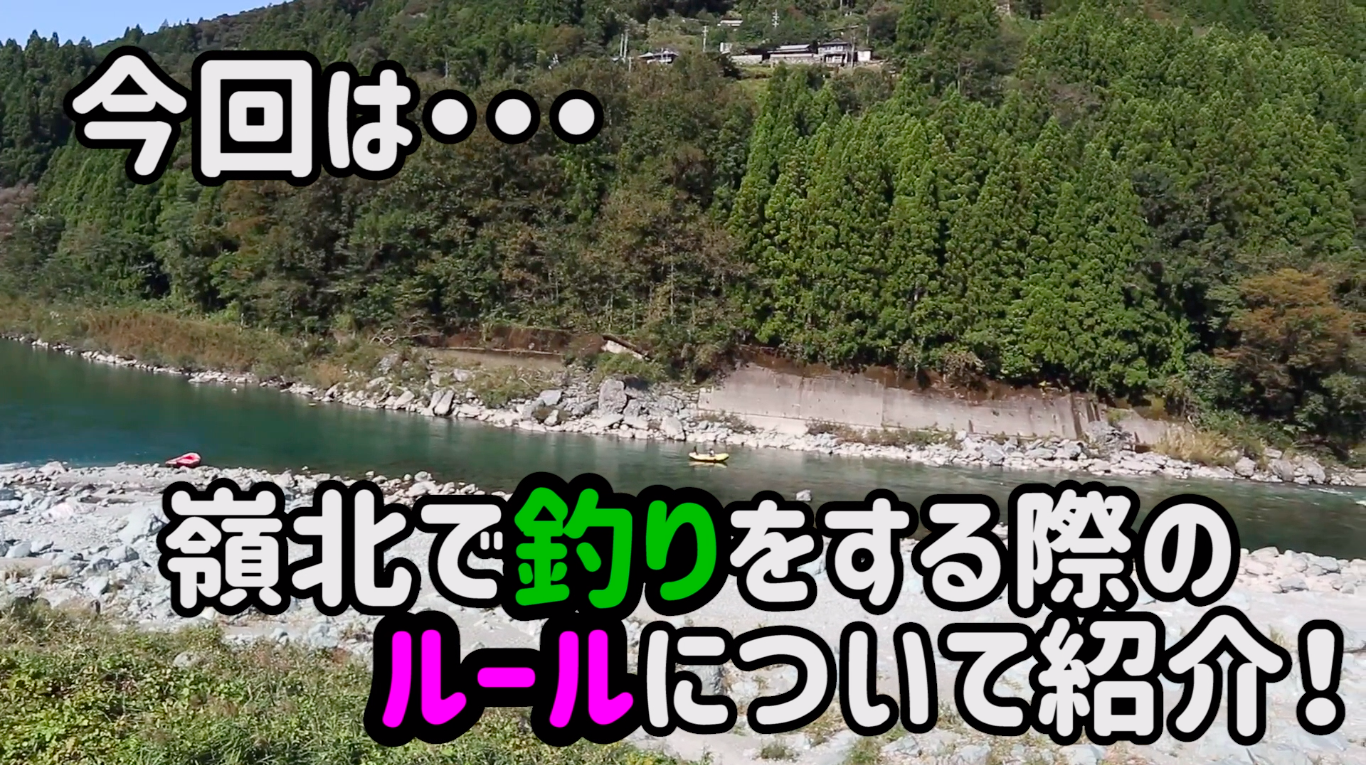

コメントを残す